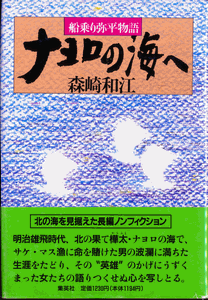

森崎和江は永野弥平の孫である函館大学永野弥三雄教授から「船乗弥兵衛関係文書−明治期樺太漁業企業者史料」を頂いたのが縁で、西海や函館を訪れて弥平の足跡を辿り、「ナヨロの海」を執筆した。1988年5月集英社
石川県と北方領土にもあるように、石川の先達は北海道、北方4島、樺太で活躍している。志賀町安部屋出身で樺太に最初の漁場を拓いた豪商村山伝兵衛に引続いて、弥平も樺太で大活躍をし、北洋漁業の先駆者といわれる。
函館市史にもその頃の漁の様子が描かれている。
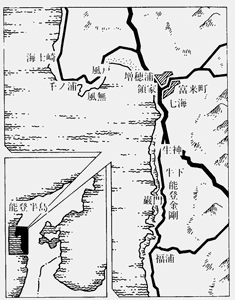
天保3年(1832年)石川県能登国羽咋郡西海村字風無68番地に生まれた弥平は、14歳で父親を失い、15歳で祖父母を残して北前船に乗り、炊(かしき)として炊事などの雑役を行った。
普通、炊を2〜3年すると若衆と呼ばれる水手(かこ、後に水夫)になり、数年して能力に応じて三役(表と呼ぶ航海士、知工という事務長、親父と言われる水夫長)になる。
慶応4年(1868年)に36歳で江戸の永代橋にあった美濃屋長左衛門によって、住吉丸の船頭になった。
弥平は三役になってからも、漁期明けに帰村することもなく、江戸永代橋の店を手伝っていたが、落ちこぼれた米を丹念に拾っていた事が評価され、船頭に取り立てられたという。
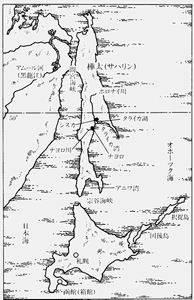
明治2年には函館港が榎本軍によって封鎖されていたが、弥平たちが夜半に潜って索条を切断し官軍の兵士の上陸を助けた事から、恩賞を受けている。
美濃屋は加納藩(岐阜県)が藩財政を確保するために加納藩士の長野長十郎に商売させていたものだが、藩主の永井肥前守は官軍の役に立ち、藩主の立場も救ったということで、永井と長野から一字ずつ与えて永野と名乗ることを許した。
慶応元年(1865年)に長野長十郎が加納藩の漁場をボロナイ川河口に拓いたが、弥平はそこでの漁を任されたようだ。
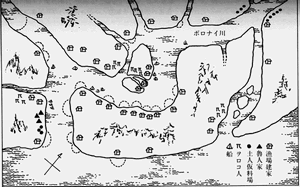
ナヨロとはアイヌ語で「川のところ」という意味だそうだが、ナヨロの海はボロナイ川とナヨロ川の河口にあたり、鮭鱒が上る好漁場だったようだ。
網の長さは160間(約290メートル)で25人がかりで曳き、1網で800石の漁獲があった。1割の80石をお上に運上し、5分の36石を函館港の雑費、とし江戸で売れば、3300両の収入から漁に必要な塩、網、米、味噌、漁夫の給料などを引けば利益は1800両。
弥平は独立を願い出て許され、さらに住吉丸の使用も許され、ナヨロでの漁業権を得る。
サケマス漁には曳き網が使われていたが、弥平は鰊漁で使われていた建網(定置網)を仕掛け、大漁が続く。
現地ではアイヌを雑夫として雇い、米、煙草、、酒、古着などを日本人漁夫の半額程度を基準に支払ったため、利益は莫大なものとなった。
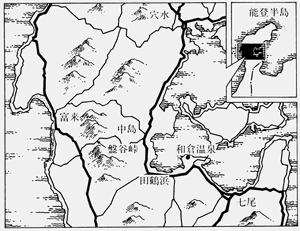
弥平は「フタッチャの旦那様は和倉で遊び、駕籠に乗って盤谷(ばんたに)峠をお金ばら撒きながら帰りなさった。」と言われるほど故郷に羽振りを利かせたようだが、その家庭環境は決して幸せだったとは言えないようだ。
風無の本家には最初の妻との間にやえ、本倉家から来た次の嫁との間にやよが、さらに函館で越中きよと所帯を持ち、やのが生まれたが、いずれも女の子だったため、千浦の新沢喜作の次男直次郎を養子に迎える。
弥平が51歳の年(明治16年)に、きよに長男直造、次の年に次男英造が、本家に三女やいが誕生したが、その妻は明治19年に病死し、直次郎の姉みやを本家の嫁に迎え、直次郎との養子縁組を解く。
弥平が60歳の年にみやに長男弥三吉が生まれるが、廃嫡とし、西海村風戸の大庭修平の次男種吉を婿養子としてやよと結婚させる。
しかし、やよの初産が難産となり、やよも子供も亡くなってしまう。
弥平は種吉を「行状正しからざる」として離縁し、弥三吉の廃嫡を解く。

小川 弥四郎 (おがわ やしろう) 1846年〜1914年
弥平の祖父の生家ヤシロの長男。明治初年函館に渡り、永野弥平の支配人として樺太漁業に従事した。
露領沿海州ニコラエフスクに渡航して鮭鱒の買付事業を始め、以後50年間にわたり北洋漁業の経営に当たった小川合名会社の創立者・小川弥四郎。
明治28年、独立して、女婿の坂本作平を伴い、露領沿海州ニコラエフスクに渡航して鮭鱒の買付事業を始める。以後50年間にわたって北洋漁業の経営に当たる。
その他に名前が出ている志賀町出身の人として、P56「生神の橋本六三郎」「風戸の谷内太八郎」、P65「風戸の松本長太郎」「風無の大崎元吉」、P99「風無の笹野文七」、P104「高浜の宮崎藤松」「高浜の若狭友三郎」、P250「風無の端野しな」「同郷の儀太郎」

行動派作家として知られる立松和平氏が表紙の帯に書評を載せておられる。
なお、先週(2010.2.8)、立松氏は亡くなられた。ご冥福をお祈りする。
北の苛酷な漁場を舞台にした叙事詩だと思ったのだった。
感情を極力排した淡々とした筆の運びによって描かれるのは、壮大なスケールの民衆史だ。
著者は弥平なる人物を愛情を込めて造形していく。その筆の運びは精緻をきわめる。記録も散逸しているだろうし、古いことなので生きた証人もいない。
しかし、弥平の手記があったという幸運に恵まれたにせよ、今では私たちは足を踏み入れることも困難なサハリンのナヨロの海を、まるで現場に立ったかの
ように描ききる力量はなみなみではない。